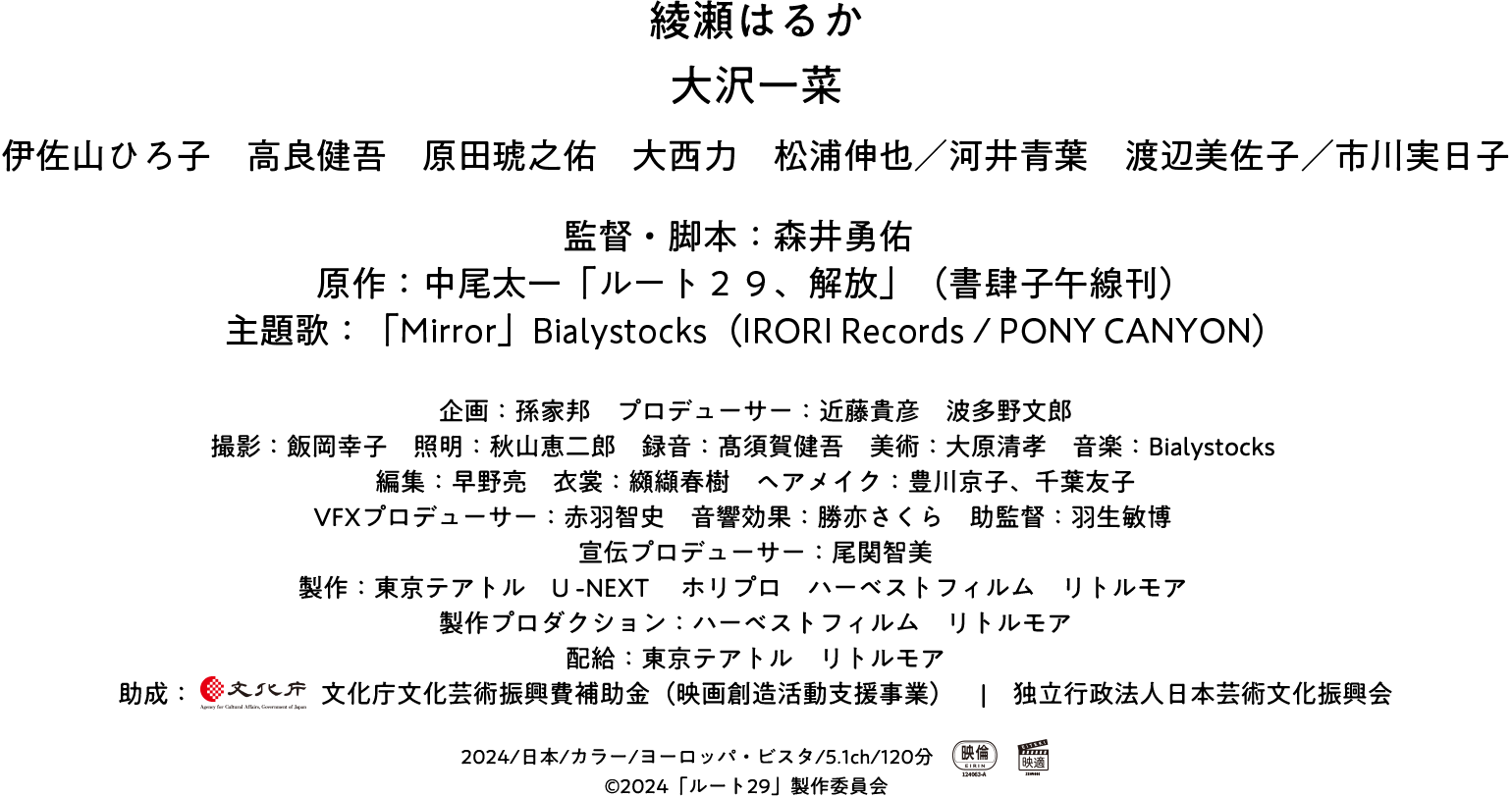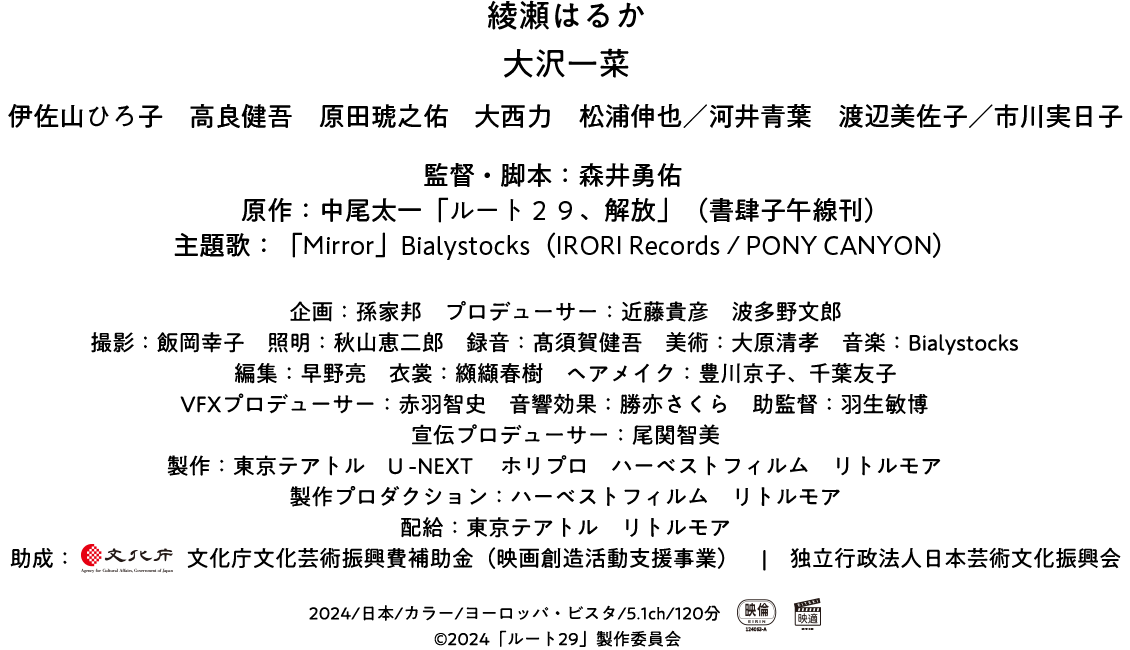彼女たちは落第した妖精のようにも見える。二人は道を歩き、道で眠り、道で夢を見る。
そこでどこか悲しげで滑稽な人たちと出会っては別れていく。
そのゆるやかな連帯=ファンタジーの大らかさが寂れた国道を一陣の風のように吹き抜けていく。
中尾太一 (詩人、原作者) /オフィシャルプログラム内寄稿より抜粋
何かを思うより先に、見ていて「必要な映画だ」と思った。ある人にとってはとても必要な映画になるだろう、って。泳ぐため、飲むため、そんな水そのもののような「必要」がこの映画にはある。
最果タヒ (詩人) /オフィシャルプログラム内寄稿より抜粋
二人の旅は、あらゆる汚れを弾きながら無垢であり続けるための道となる。雨上がりの澄んだ空気と、空の明るさを映す水たまり、二人がそれをわざと踏んでいく姿。そういうものは私が旅の中で見る美しさと同じようにそこにあって、私は少し混乱した。しかし同時に、確かにそれを歩いた二人の記憶を祝福したい気持ちに駆られるのだった。
乗代雄介 (小説家) /オフィシャルプログラム内寄稿より抜粋
「風」が監督に味方している。強弱あいまいな風が画面いっぱいにふくれる緑と、切り裂く光としてあばれ回っていた。
椎名誠 (作家、エッセイスト) /オフィシャルプログラム内寄稿より抜粋
「夢」に似ているのではない。「夢」が生まれる場所、わたしたちみんながかつていたことのある場所。わたしたちの「脳」が、意味や物語に蝕まれる以前に棲息していた場所なのだ。わたしたちはみんな、あそこから来たのだ。だから、ひどく懐かしい気になるのだ。
高橋源一郎 (作家) /オフィシャルプログラム内寄稿より抜粋
いま・ここにある世界が生きにくい者たちのために、もうひとつの新たな世界が創出され、優しい御伽話がそっと紡がれてゆく。
児玉美月 (映画文筆家) /オフィシャルプログラム内寄稿より抜粋
「わたし」は一人称のくびきを脱して「あなた」へと溶け出し、「あなた」もまた二人称を逸脱して「わたし」にも「わたしたち」にもなる。「わたし」の中に「あなたたち」を発見する。旅路の果てに、のり子とハルは鳥取砂丘に到達し、かけがえのない時間を共にする。ふたりは海に視線を投げかけながら言葉を交わすが、波の音が聞こえるばかりで、カメラは視線の先にあるはずの海を決してとらえることがない。高低差なき平衡化した視線の到達点は不可侵のものであり、わたしたち観客でさえ入り込む隙間がないのかもしれない。
荻野洋一 (映画評論家) /オフィシャルプログラム内寄稿より抜粋
森井勇佑二作目、こう来たか! ウェス・アンダーソンをも彷彿とさせるシンメトリカルかつカラフルな画面デザインのなか、さらにスケールアップした天才的異物感で突き抜ける大沢一菜と、大きな瞳をより見開いて世界を再発見してゆくかのような綾瀬はるか……この一種「ありえない」コンビネーションが、道中の奇妙な出会いを通じて、オフビートな化学反応を起こしてゆく。そんな国道沿いのマジックリアリズムに、いつしか観る者の心にも、なんだかいい風が吹きはじめるのだ。
宇多丸 (RHYMESTER)
森井監督の撮る一菜さんが大好きです。このふたりの結びつきでないと撮れない表情があることが伝わってきます。いつでも彼女がのびのびと自由でありますように。見守っています。
青葉市子 (音楽家)